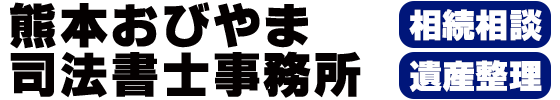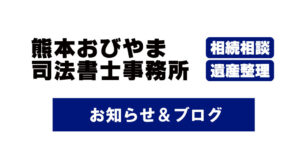制度開始から1年経過した「相続登記義務化」を熊本の司法書士が徹底解説!
【相続登記の義務化】とは?自分でできる?熊本の司法書士が徹底解説
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化され1年以上が経過しました。これは、長年にわたり問題となっていた「所有者不明土地」への対策として、法改正により導入された制度です。
この記事では、司法書士として相続手続きに多数携わってきた立場から、制度の概要・背景・手続きの詳細・自分で登記する手順・司法書士に依頼する場合の違いをわかりやすく解説します。
第1章|相続登記の義務化とは?背景と制度の全体像を徹底解説
2024年4月1日、不動産登記法が大きく改正され、「相続登記の義務化」がついにスタートしました。これにより、相続によって不動産を取得した人は、一定期間内に相続登記を申請する義務が課されることになりました。
これまで「義務ではなかった」相続登記が、なぜ今になって法律で強制されるようになったのか。その背景には、社会全体を揺るがす深刻な問題があります。
❶ 相続登記とは? ― 不動産の名義を相続人へ移す手続き
そもそも「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きをいいます。
たとえば、父親が土地を所有しており亡くなった場合、その土地の登記簿上の所有者は「故・父親」のままです。この名義を、長男や配偶者といった相続人の名義に変える手続きが相続登記です。
✅ 重要: 相続登記をしていないと、不動産の売却・担保設定・建て替えなどができません。
❷ これまで相続登記は「義務ではなかった」
意外かもしれませんが、2024年以前は、相続登記は法律上の義務ではありませんでした。
そのため、亡くなった人の名義のまま何十年も放置されるケースが全国で多数発生しました。特に地方や田舎の土地、山林、農地などは「使い道がないから」「兄弟が遠方に住んでいて協議が進まない」などの理由で手続きが放置されがちでした。
▼【比較表】これまでと今後の違い
| 項目 | 旧制度(~2024年3月) | 新制度(2024年4月~) |
|---|---|---|
| 相続登記 | 任意(手続きしなくても罰則なし) | 義務(原則3年以内に申請) |
| 期限 | なし(何年放置してもOK) | 相続を知った日から3年以内 |
| 罰則 | なし | 10万円以下の過料あり |
| 所有者不明問題 | 放置され拡大 | 解消に向けて動き出す |
❸ 義務化の背景|深刻な「所有者不明土地」問題
相続登記の義務化のきっかけとなった最大の要因が、所有者不明土地問題です。
この問題は、所有者が亡くなった後も相続登記がされず、名義が古いままの不動産が全国に広がってしまったことにあります。とくに地方では、地元を離れて暮らす相続人が「登記をせずに放置する」ケースが多発していました。
【データで見る所有者不明土地の現状(国土交通省調査)】
- 全国の約22%の土地が、所有者不明
- 面積にすると九州本島全体に匹敵
- 公共事業・災害復旧・地域活性の妨げに
- 固定資産税の徴収も困難になる
このような問題を解消すべく、政府は2021年に「所有者不明土地問題対策法」などを含む一連の改正法案を成立させ、その柱の1つが相続登記の義務化でした。
❹ 相続登記義務化の概要|期限・罰則・対象を整理
制度の全体像を、ポイント別に整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2024年4月1日 |
| 対象 | 被相続人が亡くなり、不動産を相続したすべての相続人 |
| 義務の内容 | 不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請 |
| 罰則 | 正当な理由がなく怠った場合、10万円以下の過料 |
| 過去の相続も対象? | はい。過去に発生した相続で未登記のものは、 2027年3月末までに申請が必要 |
※注目ポイント: 30年前の相続でも、登記していなければ今から3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。
❺ 熊本でも急増中!義務化にともなう相談件数
熊本県内でも、「親名義のまま土地が放置されている」「相続人が多くて登記できていない」といった相談が、司法書士事務所に急増しています。
特に以下のような方は注意が必要です:
- 親からの田畑・山林をそのままにしている
- 「自分が住んでるから大丈夫」と思って放置している
- 兄弟間で話し合いが進まず、登記できないまま
相続登記は、義務化されただけでなく、将来的に二次相続(孫への相続)にも関わってきます。早めに手続きしておくことが、将来のトラブルを防ぐカギです。
✅ まとめ:義務化された今、早めの対応が最善策
- 相続登記は2024年4月から義務化
- 登記しないと10万円以下の過料の可能性
- 古い相続も3年以内に対応が必要
- 放置していると売却・相続税対策にも影響
👨⚖️ 司法書士のひとこと:
「義務化されても、相続登記は書類収集や申請が複雑です。早めに専門家に相談することで、登記ミスやトラブルも防げます。特に複数の不動産がある方や相続人が多い場合は、ぜひお早めにご相談ください。」
📌 相続・遺言のことで迷ったら、まずは気軽にご相談を。
第2章|相続登記を自分で行う場合の手順と必要書類を完全解説
「費用を抑えたい」「時間はかかっても自分でやりたい」──そんな方のために、相続登記を自分で行う方法をステップごとに完全解説します。
この記事を読めば、専門家に依頼せずともご自身で法務局に相続登記を申請するために必要な書類と流れを理解できるようになります。
❶ 自分で相続登記する場合の全体の流れ
相続登記を自力で行うには、以下のような手順になります。
| ステップ | 作業内容 |
|---|---|
| STEP1 | 被相続人の戸籍を出生から死亡まで収集 |
| STEP2 | 相続人全員の戸籍と住民票を取得 |
| STEP3 | 遺産分割協議書の作成(協議が必要な場合) |
| STEP4 | 固定資産評価証明書の取得 |
| STEP5 | 登記申請書の作成と必要書類の準備 |
| STEP6 | 法務局に提出(窓口または郵送)・管轄に注意 |
※法務局は「管轄」があるので、不動産所在地の管轄局を必ず確認しましょう。
❷ 必要な書類一覧と入手方法
相続登記に必要な書類は多岐にわたります。以下に具体的な一覧をまとめました。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| ①被相続人の戸籍(出生~死亡) | 本籍地の役所 | 死亡日から逆算し出生まで。結婚・転籍などに注意 |
| ②被相続人の除票または住民票の除票 | 最終住所地の役所 | 不動産所在地との紐付け確認のため |
| ③相続人全員の現在戸籍 | 各自の本籍地 | 本人確認と法定相続人の確定用 |
| ④相続人の住民票 | 各自の住所地の市区町村役場 | 登記簿に反映される・名義人とならない場合は不要 |
| ⑤固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 登録免許税の算出に必要(1月1日時点の評価) |
| ⑥登記申請書 | 自作または法務局HP | 以下で書き方解説 |
| ⑦遺産分割協議書 | 自作(全員の署名・押印が必要) | 印鑑証明書を添付 |
| ⑧相続関係説明図 | 自作 | 戸籍に基づいて作成 |
※戸籍は一通では足りません。被相続人が転籍していた場合、複数の市区町村から取り寄せる必要があります。
また、それぞれの事情により必要書類は変わってきますので注意が必要です。
❸ 書類作成の具体例|記載のポイント
◆ 登記申請書(例:単独相続の場合)
登記の目的 所有権移転 原因 令和5年5月1日相続 相続人 (被相続人●●) 何某 添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 など 課税価格 3,000,000円 登録免許税 12,000円(課税価格×0.004) 不動産の表示 (登記簿に記載されている通り記載)
※詳細は法務局HPを参照してください。
◆ 相続関係説明図(例)
以下のように簡易な家系図を作成し、戸籍に基づいて関係性を記載します。
被相続人:山田一郎(昭和30年生、令和5年死亡) | -------------------------------------- | | | 長男:太郎 長女:花子 次男:次郎
Wordや手書きでも可です。複雑な家系の場合は司法書士に相談するのが無難です。
❹ 登記の申請方法|窓口・郵送・オンライン
申請方法は主に以下の3つがあります。
- 窓口申請:管轄法務局に書類一式を提出。
- 郵送申請:遠方に住んでいる場合に便利。返信用封筒を同封する。
- オンライン(登記ねっと):一部対応。ただし一般向けには難易度が高め。
おすすめは窓口持参か郵送。登記官のチェックも丁寧です。
❺ よくあるミス・注意点まとめ
| よくあるミス | 解説・対策 |
|---|---|
| 戸籍が一部不足している | 出生から死亡まで「空白なし」で揃える必要あり |
| 評価証明書が古い | 当該年度(4月~翌年3月)最新版を取得する |
| 協議書に印鑑証明が添付されていない | 相続人(全員)の印鑑証明書を必ず添付(3ヶ月以内) |
| 登記簿の記載と違う住所を申請書に書いている | 住民票上の住所を正確に記載する |
✅ まとめ:自分で相続登記を行うには「調査・正確さ・丁寧さ」が鍵
- 戸籍の収集は「出生から死亡」まで必須
- 遺産分割協議書には印鑑証明付きで署名押印が必要
- 書類ミスは登記却下のリスクにつながる
- 評価証明や登記簿情報は最新版を使用
📌司法書士からのアドバイス:
「戸籍が複雑だったり、協議が難航している場合は、自力登記はかなりハードルが高くなります。悩む前に一度、専門家に相談するのも選択肢の一つです。」
第3章|相続登記を司法書士に依頼する場合の手続き・費用・メリットを徹底解説
相続登記は自分でもできるとはいえ、専門性の高い知識と煩雑な書類作成が求められる手続きです。特に相続人が複数いたり、不動産が複数ある場合、ミスやトラブルのリスクも高くなります。
そうしたリスクを回避し、安心して手続きを進めるために多くの方が選んでいるのが司法書士への依頼です。
この章では、司法書士に依頼した場合の手続きの流れ、費用の目安、具体的なメリットについて詳しくご紹介します。
❶ 司法書士に依頼した場合の基本的な流れ
相続登記の相談から完了までは、以下のようなステップで進みます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 無料相談・ヒアリング(面談または電話・オンライン) |
| STEP2 | 必要書類の収集(戸籍・評価証明書など)を代行 |
| STEP3 | 遺産分割協議書の作成サポート |
| STEP4 | 相続関係説明図の作成 |
| STEP5 | 登記申請書の作成と提出(法務局への申請) |
| STEP6 | 登記完了・登記識別情報の受け取り |
👉 ご本人がやることは、「最初に相談すること」と「印鑑証明書を用意すること」くらいです。
❷ 相続登記を司法書士に依頼する際の費用内訳
司法書士への依頼費用は、「司法書士報酬」と「実費(登録免許税・戸籍取得代など)」に分かれます。
▼ 費用の目安(標準的な相続のケース)
| 項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 司法書士報酬 | 7万円~10万円前後 | 不動産の数や相続人の数によって変動 |
| 戸籍・評価証明の取得代行 | 1万円~3万円 | 取得通数や本籍地による |
| 登録免許税 | 不動産評価額 × 0.004 | 固定資産評価証明書に基づく |
| 郵送・印紙・交通費など | 数千円程度 | 実費 |
☑ 総額の目安: 10万円~20万円前後(登録免許税込み・ケースによる)
費用はかかりますが、「ミスのない正確な手続き」と「安心感」が得られる点で非常にコスパが高いといえるでしょう。
❸ 司法書士に依頼する主なメリット
相続登記を司法書士に任せることには、以下のような大きなメリットがあります。
◆ ① 書類の調査・収集を丸ごと任せられる
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査・取得
- 全国の本籍地にまたがる場合でも対応可能
- 住民票・除票・評価証明書なども取得代行
◆ ② 複雑なケースにも対応可能
- 相続人が海外在住・行方不明
- 代襲相続・養子縁組・婚外子など特殊な事情
- 相続関係が複雑な家系図でも整理して手続き
◆ ③ ミスなく正確な申請ができる
- 登記ミスで却下される心配がない
- 登記内容や表現ミスによるトラブルを回避
- 不動産売却や贈与を前提とした登記内容の相談も可能
◆ ④ 将来的な手続きまで一括サポート
- 売却、贈与、信託、名義変更などにも連携
- 相続税や遺言作成、家族信託などの相談も可能
- 他士業(税理士・行政書士)と連携してワンストップ対応
❹ 自分でやる場合との違いを比較表でチェック
| 項目 | 自分で登記 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税+実費のみ(約1万~10万円+税) | 10万円~20万円程度(登録免許税込み) |
| 手間・時間 | 戸籍調査・書類作成・申請すべて自力 | 大半を代行、最短で完了 |
| ミス・却下リスク | あり(専門知識が必要) | ほぼゼロ(プロが対応) |
| 特殊事情への対応 | 難しい | 可能(調整・法的根拠に基づく処理) |
| 将来の相談 | 対応不可 | 相続税対策・売却相談など継続対応可能 |
💡結論:「時間と安心」を重視するなら司法書士への依頼がベストです。
❺ 熊本で相続登記を依頼するなら|地域密着の司法書士が安心
熊本では、「両親の土地がそのまま」「古い名義がずっと放置」されているケースが非常に多く、相続登記義務化により対応を迫られる方が増加中です。
地元の事情や土地勘を熟知した地域密着の司法書士に相談することで、スムーズで安心な手続きが可能になります。
📩 無料相談受付中|まずはお気軽にご相談ください
・うちは義務化の対象になるの?
・昔の土地でも登記しなきゃいけない?
・登記をしないままだと売却できないの?
些細なことでも構いません。専門家が丁寧にご案内いたします。
第4章|相続登記 義務化 比較:自分でやるか?司法書士に頼むか?徹底判断ガイド
2024年4月から始まった相続登記の義務化により、これまで放置されがちだった名義変更手続きを避けては通れなくなりました。
では、その登記手続きを「自分でやるか?」「司法書士などの専門家に頼むか?」、どちらが良いのでしょうか。
この章では、読者の状況に応じた判断基準と比較表をもとに、ベストな選択ができるよう解説します。
❶ まず整理:相続登記 義務化のポイントを再確認
比較をする前に、義務化の内容を簡潔に整理しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 相続によって不動産を取得した人 |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の相続も対象? | 対象(2027年3月末までに登記が必要) |
| 罰則 | 正当な理由がなく申請しない場合は10万円以下の過料 |
📌 POINT: 義務化された以上、登記をしない選択肢はありません。問題は「誰が・どうやってやるか」です。
❷ 相続登記を「自分でやる」場合のメリット・デメリット
コストを抑えたい方や、法務局や役所に慣れている方は、自分で登記するという選択肢も可能です。
▼ メリット
- 費用が安い(登録免許税+証明書実費程度)
- 自分で内容を把握しながら進められる
- 法務局の相談窓口(要予約)を活用できる
▼ デメリット
- 戸籍収集が非常に大変(出生から死亡までの全戸籍)
- 書類の作成や記載ミスで登記が却下されることも
- 相続人が多い、トラブルがある場合は処理できない
- 調べながら手続きするため時間がかかる
❸ 専門家(司法書士)に依頼する場合のメリット・デメリット
安心・確実に手続きを終えたい方や、相続が複雑なケースには、司法書士への依頼が圧倒的におすすめです。
▼ メリット
- 戸籍調査・書類作成・申請までフルサポート
- 不動産が複数・相続人が多数でも対応可能
- ミスがないので登記却下のリスクがほぼゼロ
- 将来の不動産売却や二次相続にもつながるアドバイスあり
▼ デメリット
- 費用がかかる(10万円~20万円程度)
- 一部書類(印鑑証明など)の取得は依頼者も必要
❹ 比較表|自分でやる?専門家に任せる?
「相続登記 義務化 比較」の視点で、自分でやる場合と司法書士に頼む場合の違いを明確に比較してみましょう。
| 比較項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に頼む場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 数千円~10万円(実費のみ) | 10万~20万円前後(報酬+実費) |
| 必要な労力 | 戸籍調査・申請・作成などすべて自力 | ほぼお任せでOK |
| 書類ミス・却下のリスク | あり(専門知識が必要) | なし(経験豊富な専門家) |
| トラブル時の対応 | 自己解決が必要 | 法律に基づいた対応が可能 |
| 時間 | 数週間~1ヶ月以上かかることも | 最短1~2週間で完了可能 |
| 安心感 | 不安や疑問を自己解決 | 随時相談できる安心感 |
結論:「時間と安心」を重視するなら専門家へ。「費用重視」で手間を惜しまないなら自力も可能。
❺ 判断基準チェックリスト|こんな方は司法書士に相談を!
以下に当てはまる方は、司法書士に相談することでスムーズかつ確実に相続登記が進みます。
- 被相続人の戸籍が複雑で、自分で収集するのが難しい
- 相続人が複数いて、協議が必要(遺産分割協議書が必要)
- 不動産が複数ある・評価額が高い
- 不動産を将来的に売却・活用したい
- 相続トラブルや認知症など、将来の不安も含めて相談したい
司法書士は「相続登記の専門家」です。税務・信託・遺言・売却サポートまで視野に入れて相談できます。
まとめ|相続登記 義務化の今こそ、自分に合った方法を選ぼう
- 2024年から相続登記は義務化され、放置できない時代へ
- 費用・時間・手間・将来性を比較してベストな選択を
- 「比較して迷ったら」まずは無料相談を活用
📩 相続登記で迷ったら…お気軽にご相談ください
「自分でできると思っていたけど、途中でつまずいた」
「古い土地の相続登記、どうすればいい?」
そんな時は、熊本の司法書士が丁寧にサポートいたします。
📌 相続・遺言のことで迷ったら、まずは気軽にご相談を。
第5章|よくある質問Q&A(相続登記 義務化・比較・手続き)
ここでは、2024年から始まった相続登記の義務化に関する「よくある質問」をQ&A形式で整理しています。
「自分でやる?専門家に依頼?」という判断のためにも、ぜひ参考にしてください。
Q1. 相続登記は本当に義務になったのですか?
はい、2024年4月1日から相続登記の申請は義務となりました。相続によって不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
Q2. 義務化以前の相続(たとえば20年前)も対象ですか?
はい、過去の相続も対象です。2024年4月1日時点で相続登記が未了の場合、3年以内(=2027年3月31日まで)に登記申請を行う必要があります。
Q3. 相続登記をしないと何が起こりますか?
10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。また、不動産の売却・担保設定・建て替えなどができず、将来の相続トラブルにも発展しかねません。
Q4. 相続登記は自分でできますか?
可能です。必要書類をすべて自力で集め、登記申請書・相続関係説明図・遺産分割協議書などを自作し、法務局に提出することで手続き可能です。ただし、戸籍の読み取り・申請内容ミスによる却下などには注意が必要です。
Q5. 自分でやる場合の費用はいくらぐらいですか?
最低限必要なのは登録免許税(不動産評価額の0.4%)と、戸籍・評価証明書などの取得費用です。合計で1万円~10万円台で済むケースが多いです。
Q6. 司法書士に依頼する場合の費用相場は?
司法書士報酬が6万円~10万円程度、その他に登録免許税・実費がかかります。全体で7万円~20万円程度が一般的な相場です。
Q7. 相続人が複数いる場合、自分で手続きできますか?
可能ですが、遺産分割協議書の作成と、全員の署名・押印+印鑑証明書が必要になります。関係が疎遠だったり、調整が難しい場合は司法書士のサポートが推奨されます。
Q8. 不動産が遠方(別の県など)でも登記できますか?
はい。法務局への郵送申請が可能です。また、司法書士に依頼すれば、遠方でも現地法務局に対応してもらえます。
Q9. 途中まで自分でやったが、わからなくなってしまいました。司法書士に途中から依頼できますか?
もちろん可能です。戸籍の一部や申請書の途中段階でも、司法書士が内容を確認して引き継ぎ可能です。無駄にならないよう書類はすべて保管しておきましょう。
Q10. 熊本で信頼できる司法書士を探しています。相談だけでも可能ですか?
はい、初回相談は無料で対応している事務所が多くあります。熊本県内で相続登記を多数扱っている司法書士に相談することで、地域事情や不動産特性を加味したアドバイスも受けられます。
📩 相続登記に関するご質問・ご相談はお気軽に
「何から始めればいいのかわからない」「義務化の期限に間に合うか不安」といったご相談も歓迎です。
熊本の相続に詳しい司法書士が、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
第6章|まとめ|相続登記は「いつか」ではなく「今すぐ」取り組むべき
2024年4月から始まった相続登記の義務化。この制度によって、「放置していた不動産の名義を変えないといけない」という方が全国的に急増しています。
熊本県でも、「親の名義のままになっている土地」「兄弟と話し合っていない空き家」「祖父の代から放置されている山林」など、“今までは放っておいても何とかなっていた”相続不動産が、突然リスクの対象になったケースが非常に多く見られます。
❶ 相続登記を放置すると、時間もお金も「倍以上」かかる可能性
「今は使っていない土地だから」「相続人同士で揉めてないから」と安心していても、数年後に次の相続(いわゆる二次相続)が起きると、手続きは格段に難しくなります。
- 相続人がさらに増える(兄弟の配偶者・子など)
- 知らない相続人と話し合わなければならない
- 共有持分が複雑になり、売却・活用ができない
- 将来的に“負動産(ふどうさん)”になる可能性も
POINT: 登記を先延ばしにすればするほど、「手間」「時間」「費用」が跳ね上がり、子や孫の代にまで負担がのしかかることになります。
❷ 自分でやるか、専門家に任せるか──「迷う時間」がいちばんもったいない
相続登記は、自分で行うことも可能です。しかしそのためには、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
- 不動産評価証明の取得
- 登記申請書や相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成と印鑑証明書の添付
といった煩雑で専門性の高い作業が必要になります。
「途中でわからなくなった」
「戸籍の解読に時間がかかりすぎた」
「法務局に行っても結局解決できなかった」
そうした声は、当事務所でも多く聞いています。
✔ 迷った時点で、まずはご相談ください。相談の段階でお金が発生することはありません。
❸ 熊本の司法書士として、相続登記に強い理由があります
当事務所では、熊本エリアに特化した相続登記を数多く取り扱っており、以下のようなケースにも対応可能です:
- 古い農地・山林の名義が放置されたまま
- 空き家となった実家の売却を検討している
- 複数の相続人が県外に住んでいて連絡がつきにくい
- 被相続人が何度も転籍していて戸籍が複雑
相続登記に限らず、将来的な財産管理や相続税対策、遺言・家族信託・不動産売却などにもワンストップで対応できる体制を整えています。
お客様の声より:
「役所や法務局を何度も回らずに済んだので、本当に助かりました」
「兄弟との関係が微妙だったけど、丁寧に調整してくれた」
「登記だけでなく、将来の売却の相談まで乗ってもらえた」
❹ まずは無料相談から。簡単な内容でも大歓迎です
「これって義務化の対象になるの?」「そもそも相続してるかもわからない」
そんな状態からでも大丈夫です。司法書士は“相続の入口相談窓口”として動ける法律専門職です。
相談は対面だけでなく、電話・メール・LINE・Zoomでも対応しています。熊本県外の相続人がいらっしゃるケースでも、柔軟に対応いたします。
📩 相続登記のご相談はお早めに
- 「登記って必要?」という初歩的な疑問でもOK
- 現在の状況をお伝えいただくだけで、必要な対応を整理できます
- 熊本エリアに詳しい司法書士が親切丁寧に対応します
登記義務の3年ルールに間に合うよう、今から動き出すことが何より大切です。
🔚 最後にひとこと
相続登記は、一生に何度も経験することではありません。だからこそ、「正確に」「早く」「安心して」進めることが重要です。
熊本で相続に悩んでいる方のお力になれれば幸いです。
どうぞお気軽にご相談ください。
💬 熊本で相続手続きをお考えの方へ
当事務所では、熊本県内の相続放棄案件を多数取り扱っており、スピーディかつ丁寧な対応を心がけています。
土地・建物・借金・親族間のトラブルなど、どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。
▶ LINEで無料相談をする
▶ お電話: 096-234-7084(平日9時~17時)