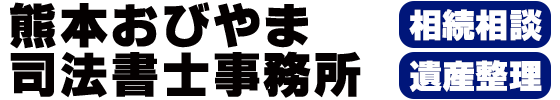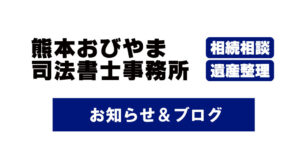失敗しない相続手続きの進め方
【熊本の司法書士が解説】失敗しない相続手続きの進め方|不安を安心に変えるガイド
最終更新日:2025年6月29日 | 著者:熊本おびやま司法書士事務所
はじめに|相続手続きは“誰にでも起こる問題”です
「相続」と聞くと、自分にはまだ関係のない話だと思われる方も多いかもしれません。
しかし、家族が亡くなったときには、必ずと言っていいほど「相続手続き」が発生します。
実際、熊本でも毎日のように相続に関するご相談をいただいています。
相続は、故人(被相続人)が残した財産を受け継ぐだけでなく、その責任や義務も引き継ぐ可能性がある重要な法的手続きです。
手続きを怠ると、不動産の名義がそのままになってトラブルのもとになることもあります。
また、法改正により2024年(令和6年)4月からは「相続登記の義務化」も始まり、3年以内に登記をしないと過料の対象になることも。
本記事では、熊本で実際に相続業務に携わる現役司法書士が、相続の基礎知識から手続きの流れ、注意点、そして「失敗しないための秘訣」まで、一つ一つ丁寧に解説いたします。
相続手続きの全体像|7つのステップでわかる流れ
相続手続きは、大まかに次の7つのステップで進めていきます。
- 1. 死亡届の提出・火葬許可証の取得
- 2. 遺言書の有無を確認
- 3. 相続人の調査と確定
- 4. 相続財産の調査と評価
- 5. 遺産分割協議の実施
- 6. 各種名義変更・相続登記の申請
- 7. 相続税の申告・納付(該当する場合)
それぞれの手続きには専門知識が必要な部分も多く、間違いや漏れがあると後々大きなトラブルに発展する可能性があります。以下で、ひとつずつ丁寧にご説明していきます。
1. 死亡届と火葬許可証の提出
家族が亡くなられた場合、まず必要なのは死亡届の提出です。通常は病院や葬儀社がサポートしてくれますが、死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されず、葬儀が行えません。
熊本では、各市町村の役所(例:熊本市中央区役所、合志市役所など)に届け出を行います。死亡届は原則として、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
2. 遺言書の有無を確認する
次に行うのは、遺言書の確認です。公正証書遺言が作成されていれば、公証役場で検索できます。
一方、自筆証書遺言が残されている場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります(※2020年以降の法改正で保管制度を使った場合は検認不要)。
熊本家庭裁判所においても、自筆証書遺言の検認申立ては頻繁に行われています。手続きには戸籍や本人確認書類、遺言書の写しなどが必要となります。
3. 相続人の確定|戸籍の取り寄せ
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
また、相続人の現在の戸籍も必要となるため、意外と手間がかかります。
熊本県内であれば市役所の戸籍課で取得できますが、他県へ転籍していた場合は全国の役所から取り寄せが必要です。
この作業に慣れていないと、何度も郵送のやり取りが発生し、数週間~1ヶ月以上かかることも珍しくありません。
司法書士にご依頼いただくと、委任状に基づき戸籍の一括収集から相続関係説明図の作成までスムーズに対応できます。
4. 相続財産の調査と財産目録の作成
次に、どんな財産が相続の対象になるのかを把握します。主な財産には次のようなものがあります。
- 土地・建物などの不動産(熊本では田畑・山林も多い)
- 預貯金、株式、投資信託などの金融資産
- 借金、保証債務、ローンなどのマイナス財産
- 動産(自動車、貴金属など)
これらを調査し、財産目録として書面にまとめることで、後の遺産分割や税申告にも役立ちます。
調査においては、通帳の履歴確認、不動産登記簿の取得、金融機関照会など専門的な知識も必要です。
5. 遺産分割協議とその注意点
相続人全員が集まって、遺産をどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。
分割が決まったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。
熊本では相続人が複数の市町村や県外に住んでいるケースが多く、郵送での調整や押印が必要になることも。
また、家族内で意見が分かれやすく、調整が難航することもあります。
第三者である司法書士が関与することで、公平かつ円滑に協議を進めやすくなります。
6. 相続登記(不動産の名義変更)
相続により取得した不動産の名義変更は、法務局への相続登記によって行います。
登記には、相続関係説明図・協議書・戸籍などの書類と、登録免許税の納付が必要です。
2024年から相続登記は義務化され、「相続を知ってから3年以内」に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
熊本県内では地目が農地や山林である場合、農業委員会の許可や届出が必要になることもあります。
このような複雑なケースでも、地元の司法書士なら実務経験に基づいて確実に対応できます。
7. 相続税の申告・納付(該当者のみ)
遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合、相続税の申告が必要になります。
申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。
熊本では、不動産の評価が比較的低めのため課税対象者は少なめですが、市街地や収益物件を所有している場合は注意が必要です。
相続税の申告には税理士のサポートが必要となることが多く、当事務所でも税理士との連携サポートを行っています。
まとめ|失敗しないための3つのポイント
- 早めに専門家に相談すること
- 財産と相続人を正確に把握すること
- 法改正(相続登記義務化など)を踏まえた対応をすること
相続は、誰にとっても初めての体験です。
手続きの煩雑さに悩まされる前に、熊本の事情を理解した司法書士にご相談ください。
あなたとご家族の大切な財産を、確実に未来へとつなげるお手伝いをいたします。