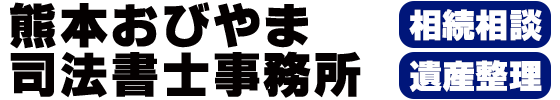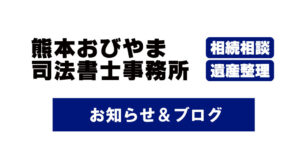遺言を書くときの注意点
遺言(ゆいごん・いごん)は、相続人に対して自分の意思を伝える重要な書類です。
遺言書を作成することで、死後の財産の分配や希望を明確にし、相続トラブルを防ぐことができます。
しかし、遺言を作成する際にはいくつかの注意点があります。
以下に、遺言を書くときの主な注意点を挙げます。
1. 法的要件を満たすこと
遺言書には法的効力を持たせるための要件があります。日本の民法において、遺言には以下の要件を満たす必要があります。
自筆証書遺言の場合
・遺言者自身が全文を手書きすること(一部パソコンで作成できる箇所もあります)。
・日付(年、月、日)を明記すること(令和7年1月吉日では×)。
・署名(遺言者の名前を自筆で書くこと)。
・捺印(印鑑を押すこと)(認め印可)。
が必要です。
公正証書遺言の場合
原則的には遺言者が公証役場に出向き、公証人が立ち会い、遺言者の意思を文書に記載します。
この場合、遺言者が自筆で書かなくてもよく、公証人と証人2人の立会いが必要です。
公証人が作成してくれるので、無効になる心配は自筆証書遺言より少ないといえます。
2. 明確かつ具体的に記載する
遺言書は曖昧さを避け、具体的に記載することが重要です。
例えば、財産の分け方や特定の遺族に対する希望について、できる限り詳細に書いておく必要があります。
・財産の特定: 何を、誰に、どのように分けるのかを具体的に記載します。例えば、「肥後銀行託麻支店普通預金○○万円を長男に渡す」など。
・不動産の場合: 不動産の住所や土地番号、登記簿の情報などを記載して、誤解を招かないようにします。不動産に関しては、登記簿通りに記載した方がよいでしょう。
3. 相続人と財産の関係を明確にする
だれが相続するかとその相続分をきちんと記載しましょう。
特に、遺産分割が複雑な場合や、特別な配慮が必要な場合(養子、後妻、前妻の子など)は、遺言書でその意図を明示しておくとよいです。
不明確な記載では余計な混乱を招くことがあります。
特別受益や寄与分: 生前贈与を受けた相続人がいる場合、その事実を遺言書に記載しておくことで、相続人間でのトラブルを防げます。
法定相続分と異なる分割: 自分の意思で法定相続分を変更する場合、その理由や分割方法をしっかりと記載しておきます。理由や想いについては、法的拘束力がないものの、自身の気持ちを子どもたちに伝えることは争族トラブルを避ける有効な手段です。
4. 遺言執行者の指定
遺言書を実行する際に、遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者は遺産の分割や相続手続きを行う役割を担います。
信頼できる人物(弁護士や司法書士など)を選んでおくと安心です。
5. 遺留分を考慮する
遺言書を書いても、法定相続人には遺留分(最低限相続できる額)が保障されています。
遺留分を侵害する内容の遺言書があった場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができ、その結果、遺言の内容とおりに相続されないこともあります。
遺言書を書く際には、遺留分を尊重するかどうかを考え、場合によっては遺言書の内容を調整する必要があります。
6. 遺言書の保管場所と管理
遺言書が見つからなかったり、改ざんされたりすると、遺言書の効力が失われることがあります。遺言書を安全な場所に保管することが重要です。
公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。
自筆証書遺言は、自宅の金庫や信頼できる人に預ける方法があります。遺言書の保管場所を家族に伝えておくと良いでしょう。
もっとも、自筆証書遺言を法務局で預かってくれるサービスもあるので、自筆証書遺言を考えている方は、そのサービスを検討するとよいでしょう。
7. 内容の更新と確認
ライフイベント(結婚、離婚、子供の誕生、財産の増減など)があるたびに、遺言書の内容を見直し、必要に応じて更新することが大切です。
古い遺言書と新しい遺言書が矛盾していると、後で混乱を招くことがあります。
新しい遺言書を作成する場合、古い遺言書を撤回する旨を明記しておくと確実です。
8. 遺言が無効になる原因
遺言書が無効とされる原因には以下のようなものがあります。
・法定要件を満たしていない(署名や日付が欠けている、証人が足りないなど)。
・意思能力が欠けていた(認知症など)。
・強制や脅迫があった(遺言書の内容が本人の自由意志によるものでない場合)。
せっかく書いた遺言を無効とならせないために、書いた遺言は専門家に見てもらうことをお勧めします。
9. 具体的な指示を加える
葬儀の希望: 自分が希望する葬儀の形式(宗教葬や無宗教葬など)、埋葬場所などを明確に記載することができます。
遺品整理: 自分が亡くなった後に、遺品をどう扱ってほしいか、どのように整理してほしいかを指定することも可能です。
もっとも、これらの記載は法的拘束力がないので、お願いベースでの記載にとどまります。
10. 証人の立会い
自筆証書遺言の場合、証人は必要ありませんが、公正証書遺言の場合、証人2人が必要となります。証人は遺言の内容に関与していない第三者である必要があり、相続人やその配偶者、直系血族は証人になれません。
11.まとめ
遺言を書く際には、法的要件を遵守し、遺言の内容を明確かつ具体的に記載することが大切です。
また、遺言執行者を選任することや、遺留分に配慮することも忘れないようにしましょう。遺言書は一度書いたら終わりではなく、状況に応じて定期的に見直し、更新することも重要です。作成後は適切に保管し、家族や信頼できる人にその場所を伝えておくとよいでしょう。
もし不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談して、適切な遺言書を作成することをお勧めします。