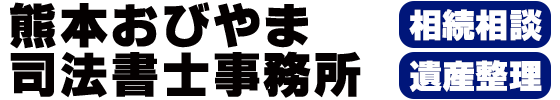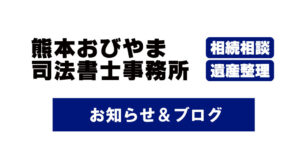相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がないことを決定し、その旨を家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人の財産や負債を引き継ぐことはありません。
相続放棄のメリットとデメリット
メリット
・被相続人に多額の負債がある場合、それを引き継がずに済む。
自身の親などにどのくらいの負債があるかを正確に把握することは難しいことです。特に、親と離れて暮らしている場合、その傾向は顕著といえるでしょう。
自身の親に予期せぬ借金がある場合でも、相続放棄をしておくと借金を引き継ぐことはないので安心といえます。
・他の相続人と遺産分割で争う必要がなくなる。
通常、遺産分割する場合、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印する必要があります。
もっとも、相続放棄すれば、放棄した者
相続が順調に進めばいいですが、非協力的な人、行方不明の人などがいて順調に進まないことも多々あります。
相続放棄をしておけば、相続における手間を省くことができます。
デメリット
・被相続人の財産(不動産や預貯金など)も一切相続できなくなる。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切放棄することになります。
そのため、借金は放棄したいが、自宅は相続したいなどということはできません。
・相続放棄をした後に撤回ができない。
一度相続放棄をすると、やっぱり辞めたといって撤回することはできません。
そのため、手続きをする前に慎重に判断する必要があります。
・他の相続人に負担がかかる可能性がある。
自身が相続放棄すると、他の相続人の相続割合が増えることがあります。
また、例えば子ども全員が相続放棄すると亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が移るということもあります。
そのため、相続放棄する場合は、他の相続人とよく相談されてから行った方がよいかもしれません。
相続放棄の手続き
1.家庭裁判所へ申述
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
ポイントは「知ってから3カ月」というところです。
死亡日から3ヶ月ではないので、期間経過して相続放棄が通るか不安な方は事前に専門家(弁護士・司法書士)に相談された方がいいでしょう。
・申述人の氏名・住所
・被相続人の氏名・住所
・被相続人との関係
・相続放棄をする旨の意思表示
などを申立書に記載する必要があります。
2.必要書類の準備
・相続放棄の申述書
・被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
・申述人の戸籍謄本
・その他、家庭裁判所が指定する書類
3.家庭裁判所での審査
申述が受理されると、家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ相続放棄が認められます。
通常、亡くなって3か月以内であれば、裁判所の審査でNGが出ることはないでしょう。
4.相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が送付され、正式に相続放棄が成立します。
もし、金融機関などから返済を求められたら、上記の書類を提出すれば、今後請求されることはありません、
特殊なケースの相続放棄
・未成年者の相続放棄: 未成年者が相続放棄をする場合、親権者が代理で手続きを行う必要があります。
・相続放棄の期限を過ぎた場合: 3か月を過ぎてしまった場合でも、特別な事情があれば期限の延長を求めることが可能です。
3ヶ月を経過した後の相続放棄は、一度専門家に相談されることをお勧めします。
・相続放棄後の相続人の変動: 先順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人(例えば兄弟姉妹など)が相続人となるため、注意が必要です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の負債を引き継がないための有効な手段ですが、慎重に判断する必要があります。
家庭裁判所への手続きや必要書類を事前に確認し、期限内に申述を行うことが重要です。
また、相続放棄をした後も、他の相続人や関係者との連絡をしっかりと行い、トラブルを避けるようにしましょう。